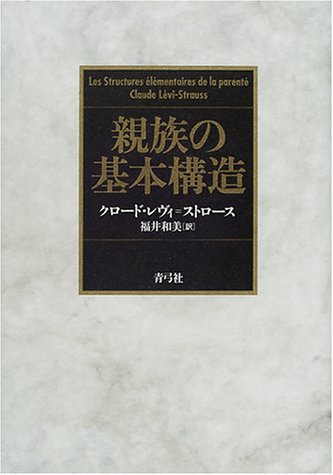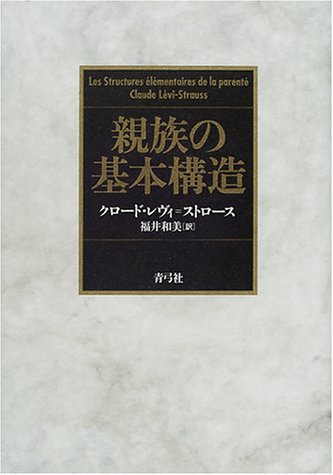モースは、人間の社会において中間的なものはないという。「完全にみずからを相手にゆだねるか、さもなければ完全に相手を拒絶するか、そのいずれかなのだ」というのである。
現代に直接に先立つすべての社会において、そしてまた、現代においてもわたしたちを取り巻いているすべての社会において、さらには、わたしたちの民俗倫理のあまたの慣習においてさえ、中間的なものなどない。完全にみずからを相手にゆだねるか、さもなければ完全に相手を拒絶するか、そのいずれかなのだ。武器を置いて呪術をあきらめるか、さもなければすべてを与えるか。しかも、すべてを与えるというのは、その場かぎりのもてなしを施すことから、娘や財を与えることにまでわたる。
マルセル・モース(森山工訳)『贈与論 他二篇』(2014年、岩波文庫)
味方でない者はすなわち敵であり、敵を味方に変えなくてはならない。そのためには疑わしい他者を歓待し、すべてを与えなければならない。そのすべてのなかには娘も含まれる。それが疑わしい他者を味方に変える方法だったのである。
このような敵を味方に変えるという贈与のシステムの中で、娘も贈与する財の中に入っている。モースによると物の取引は交換の一部を成すものにすぎず、「交換されるのは何よりも、礼儀作法にかなったふるまいであり、饗宴であり、儀礼であり、軍務であり、女性であり、子どもであり、踊りであり、祝祭であり、祭市」(同前)だったのである。女性も贈与交換されるもののなかに含まれる。しかしモースにおいて、女性だけを強調することはない。
このようなモースの考え方を推し進め、女性を交換するというアイディアのもとに家族とコミュニティの結びつきを考え抜いたのが、構造主義の提唱者として名高いクロード・レヴィ=ストロース(1908-2009)だったといえる。
レヴィ=ストロースが女性を交換するというアイディアのもとに据えたのが、人間社会に普遍的に存在するとされるインセスト禁忌だった。レヴィ=ストロースによると、インセスト禁忌はたんなる禁止を意味するものではなく、他の男性と女性を交換せよという命令であり、インセスト禁忌は、他の男性と交換すべき女性を定めた互酬規則の社会的表現だったということになるのである。(『親族の基本構造(1949)』)
インセスト禁忌はたんに禁止であるだけではない。それは「~してはならぬ」とだけでなく、同時に「~せよ」とも命じる。インセスト禁忌は、この禁忌の拡張された社会的表現である外婚と同様、一つの互酬規則なのである。人がみずからと他人に女を拒むとき、まさにそれによってこの女は供与される。(中略)すなわち、私がある女の使用をみずからに禁じ、その結果この女が別の男にとって処分権〔使用権〕の対象になる瞬間から、どこかに、ある女を権利放棄する男がおり、この権利放棄によってその女が私にとって処分権の対象になる。禁忌の内容は抑止することに尽きるのではない。禁忌が制定されるのは、直接的にか間接的にか、即座にか時間を置いてか、ただ交換を保証し基礎づけるためなのである。(福井和美訳『親族の基本構造』)
レヴィ=ストロースの言葉を自分なりに言い換えてみると、人間の家族は女性を交換するという贈与交換によって形成され、成立したのであり、インセスト禁忌はこのような女性の交換を人間に義務づけるために設定されたのだということになる。
それならばなぜ女性が交換の対象になるのだろうか。レヴィ=ストロースの説明はむつかしいので、自分なりに言い換えてみると次のようになる。
家族を、家族構成員の一部を他の家族と取り替えることによって成立するゲームだとすると、男性は取り替える対象としての価値がない。男性を取り替えたとしても家族同士のつながりは一代限りで終わり、家族の成立も一代限りで終わることになる。
家族という存在を永続させるためのゲームにするためには、女性を交換しなければならない。女性は世代を生み出す存在だからである。そのため女性は交換するための価値を持つものとなる。クラ交易における「赤い貝の首飾り(ソラヴァ)」と「白い貝の腕輪(ムワリ)」の役割を女性が果たすのである。
赤い貝の首飾りと白い貝の腕輪がそれぞれ逆方向に、2年から10年の周期でクラ交易に参加するコミュニティを一巡するように、女性は世代を重ねながら、コミュニティのあいだを循環する。クラ交易のように、女性を与えたコミュニティは、数世代後には異なるコミュニティから女性を受け取ることになる。
この贈与交換の規則を確立するために、無文字社会では複雑なインセスト禁忌の規則を作り出す。インセスト禁忌の対象となる範囲が広ければ広いほど、女性は世代を重ねながら、多くのコミュニティのあいだを循環していくことになる。
レヴィ=ストロースがどこかで書いていたことだが、オーストラリアのアボリジニは、初対面の相手とは数時間もかけて何代先もの共通の先祖を探し出し、互いに親族であることを確認するということだ。その意味するところは、互いに女性を交換する贈与のリンクに加入しているということである。この贈与のリンクに加入していない者は親族ではなく、すなわち敵ということになる。レヴィ=ストロースの説明によると、次のようになる。
彼らの社会〔無文字社会〕では、みな互いに兄弟、姉妹、従兄弟、従姉妹、叔父、叔母などの関係にあり、親族でないということは、よそものであり、潜在的な敵であるということなのです。(川田順造他訳『レヴィ=ストロース講義』)
女性の交換と潜在的な敵をつくらないことのたとえとして、レヴィ=ストロースは南フランスの大衆レストランにおける相席者どうしのワイン交換の慣習をあげる。南フランスでワインは、「一種神秘的な崇敬の念に包まれ、それゆえ典型的な《rich food》になっている」飲み物だった。《rich food》というのは贅沢品という意味である。肉や野菜は体になくてはならぬが、ワインは体にとっての贅沢品であったのである。
南フランスの大衆レストランでは、ワイン込みの値段で食事が出された。そのワインは「日替わり定食」という個人的なことがらを意味するのではなく、「神秘的な崇敬の念に包まれ」る社会的財という性質を帯びるものだった。
大衆レストランでは見知らぬ同士が相席で食事をしなければならないことが多い。
名前も職業も社会的地位もわからない人物をやりすごすのがフランス社会の習わしであるが、小さなレストランでは、そのような人物たちがほとんど肩を寄せ合うようにして一時間から一時間半も同席することになり、ときには馬が合うというので一つに結びついたりする。孤独を尊重しなくてはならないとする規範と人が集まっているという事実のあいだで、ある種の葛藤が、向かい合って座っているどちらの側にも生じている。(福井和美訳『親族の基本構造』)
このような見知らぬ者どうしの相席という葛藤を取り除くのが、ワイン交換の慣習だった。
ワイン交換はまさにこのつかの間の、しかし困難な場面に決着をつけてくれる。それは好意を明示し、相互のおぼつかない気持ちを解消し、並列状態の代わりに交流をもたらすのである。だがワイン交換はそれ以上のものでもある。それは一歩退いた態度をとる権利をもっていた相手を、そこから抜け出るよう仕向ける。ワインが供されたならワインを返さなくてはならない、親愛の情には親愛の情で応えなくてはならないのである。互いに無関心であるという関係は、会食者の一方がその関係から脱しようと意を決するや、もはやいままでとはまったく別様に結び直されずにすまない。この瞬間から関係は、もはや親愛的か敵対的かのどちらかにしかなりえない。隣席の人がワインを差し出したのに自分のグラスを差し出さなければ、礼を失するほかなく、供与を受け入れれば、それによって別の供与、会話の供与が可能になる。かくして受け取ったものよりも多くを供与することによって権利を開拓し、与えたものより多くを受領することによって義務を負うとの、つねに双方向に進む一連の相互往還運動をとおし、ささやかな社会的絆が結ばれていくのである。(前掲書)
見知らぬ者どうしが自分のワインを相手のグラスに注ぐのである。そのことによって「互いに無関心であるという関係」は成立しなくなり、「ささやかな社会的絆が結ばれていく」ことになる。
レヴィ=ストロースは、南フランスにおけるこのワイン交換の慣習を、インセスト禁忌のモデルだと指摘する。それは「未開の個体や群れが未知の個体や群れとはじめて、あるいは例外的に接触する場面」であり、そこで行われたワイン交換に類する儀礼は、女性の交換だっただろうということである。
おそらく我々はきわめて原初的な心理‐社会的経験の遺物を、いまだ新鮮なままに手にしているのであり、(中略)レストランの見知らぬ人々それぞれの態度には、ある基礎的場面が、無限遠点から、感知しがたくも識別できるほどには投影されていると我々には映るのである。すなわち、未開の個体や群れが未知の個体や群れとはじめて、あるいは例外的に接触する場面のことである。(前掲書)
南フランスの農民は自分の注文したワインの小瓶を飲むことに抵抗感を覚えるとレヴィ=ストロースはいう。この抵抗感はインセストに対する抵抗感と同じだというのである。
さて、交換なる全体的現象はまずなによりも全体的な交換であり、食べ物、制作された品物、そしてあのもっとも貴重な財のカテゴリー、女を含む。おそらく我々はあのレストランの見知らぬ客たちからずいぶん隔たったところにいる。それゆえ、自分の注文したワインの小瓶を飲むことに覚える南フランスの農民の抵抗感は、インセスト禁忌がつくりだされたときのモデルを提供する、などとほのめかせば、人々はたぶん跳び上がって驚くだろう。インセスト禁忌はあの抵抗感からもちろん出てくるのではないが、どちらも同一の文化的複合体、もっと正確に言えば、文化という基礎的複合体の要素をなす、と。しかも互酬贈与とインセスト禁忌が根本において同一であることは、ポリネシアでははっきりと目に見える。(前掲書)
「互酬贈与とインセスト禁忌が根本において同一であることは、ポリネシアでははっきりと目に見える」とレヴィ=ストロースは述べるが、ポリネシアを例に引くまでもなく、トロブリアンド諸島でもそれは明らかである。トロブリアンド諸島では兄弟は姉妹の夫に食べ物や様々な生活必需品を提供し続けなければならないが、姉妹との接触には厳格なタブーがあるとされる。
真の親族関係、真の身内は、男とその母方の親族のあいだにだけ存在すると考えられている。そのなかで、彼の兄弟姉妹は、いちばん彼に近い。ある男の一人または複数の姉妹が成長し、結婚するやいなや、彼は彼女らのために働かねばならない。それにもかかわらず、きわめて厳格なタブーが彼らのあいだにあって、しかもかなり幼いうちにこれがはじまる。姉妹のいるところでは、勝手なおしゃべりをしたり、冗談口をたたいたりしないばかりか、彼女らのことを見ようともしない。
B・マリノフスキ(増田義郎訳)『西太平洋の遠洋航海者』
人類の最大の贈与交換は、女性の交換だった。女性を交換することによって人々は親族となり、社会的な絆が結ばれていった。
近代社会は女性の交換に価値を置くことなく、個人と親族との結びつきを必要としない社会をつくりあげた。それならば、どこで贈与交換をし、どこで社会的絆が結ばれていくのだろうか。近代社会の終焉に向けて、その問いが問われなければならいといえるだろう。